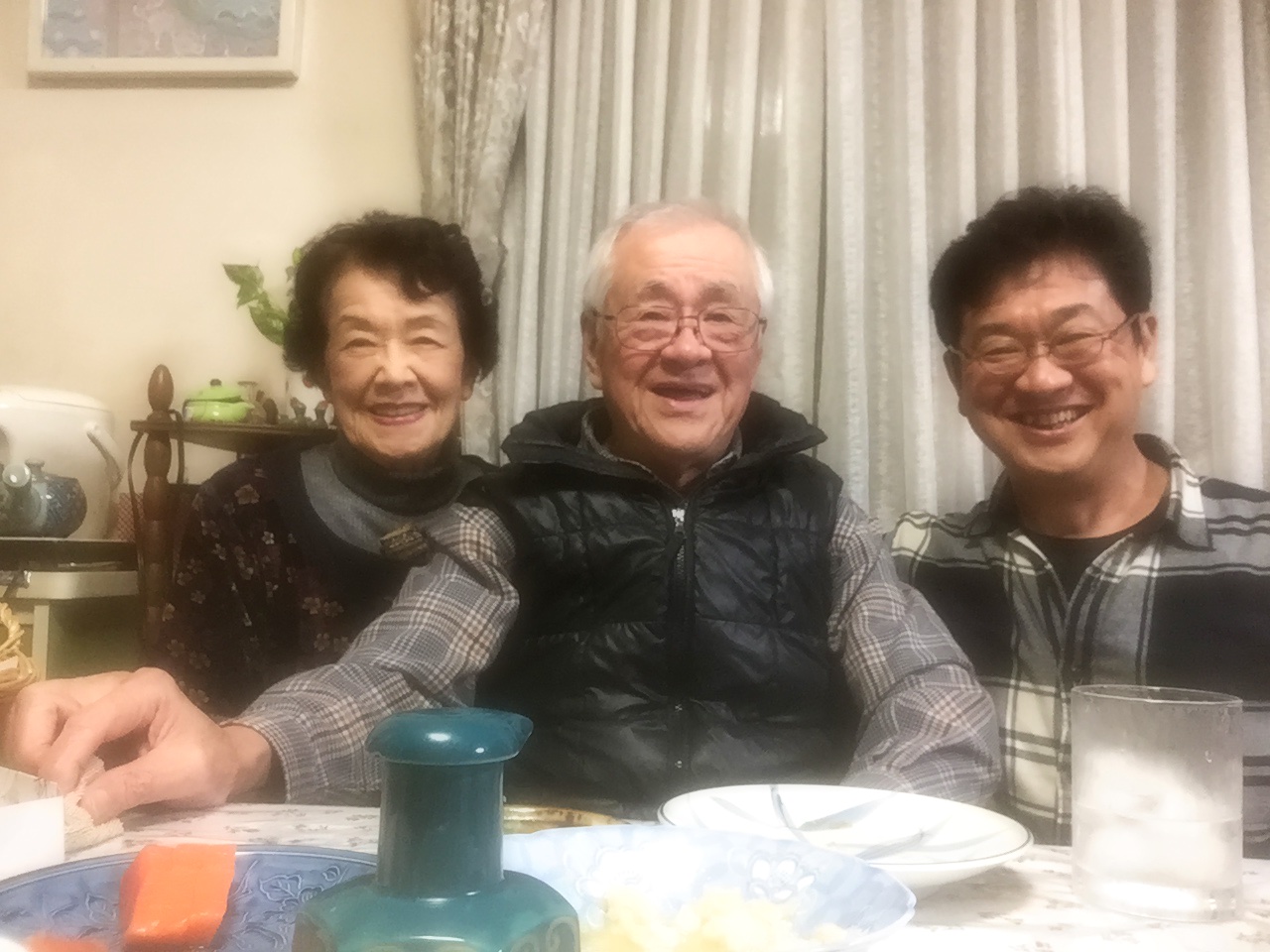「お父様の容態が急変しました。すぐ来てください」
3/25(水)の昼過ぎ、父が入院している病院から電話があった。午前中、以前から楽しみにしていたオンラインセミナーを聴講し終えた直後のことだった。
大急ぎで病院へ向かった。途中で、再度、病院から電話があった。「まことに残念ながら…お父様、本当によく頑張られたのですが…」と。覚悟はできていたが、動揺した。
病室で横たわっている父。手を握ってみた。父の手は、まだあたたかかった。幼い頃に手をつないでもらった記憶が蘇った。と同時に、こらえていた涙が一気に溢れ出した。
間違いなく父は、ずっと、この手で家族を守り続けてきてくれたのだ…その想いが心の奥底から怒涛のように湧き上がってきて、悲しみよりも、深い感謝の気持ちで、涙が止まらなくなった。
昭和3年生まれ。青春時代に戦争を経験し、復興と高度経済成長期を企業戦士として生き抜いてきた。その中で、不本意な人事異動や単身赴任など、辛く苦しい局面も多々あったろう。
しかし、いついかなる時も私利私欲は捨て、かといって高邁な精神論を振りかざすこともなく、ただ家族の幸せを考え、ものごとを判断し、真面目に働き、実直に生きて来た人生だったと思う。
寡黙で、滅多に胸のうちを明かさない父であったが、2年前に母が亡くなった直後には「長く生き過ぎた、何もしとうない、もう生きてるのも嫌や」と悲痛な声をあげた。
気をまぎらわすべく外出や食事に誘うが、首を横に振るばかり。無気力になり、認知症状も出始めた。そんな父とどう向き合い、何をすればいいのか。迷い、悩み、手探りばかりしていた、この2年だった。
91歳。大往生だったと思う。2週間前に転倒して怪我(股関節頸部骨折)をするまでは、杖も使わず自力歩行し、食事や排泄の介助も不要だった。食欲もあり、健康上も、大きな問題はなかった。
人間、死期は自分で選ぶというが、もしかしたら父は、早く母のもとへ行きたかったのかも知れない。今頃、あの世で再会し、相変わらず二人で息子(私)の不甲斐なさを心配しているのだろうか…
父が亡くなりました
 私について
私について